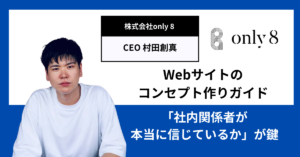今回は、ソーシャルセリングの手法を解説するインタビューです。
ソーシャルセリングとは簡単に言えば、経営者などの個人がSNSで発信し、インプレッションを伸ばし、フォロワーを獲得し、リードを獲得するようなマーケティング施策です。
SNSはサービスの投稿をして伸ばしたり、SNS広告だけ取り組んでいるという会社も多いかと思います。
また、ソーシャルセリングの手法についてどのように実施すべきか、という情報を見かけません。
今回は、ソーシャルセリングの支援サービスを行う株式会社Special One 取締役COO 木村 雄飛さんにインタビューしました。
今回は
- 「ソーシャルセリングと普通のSNS発信との違い」
- 「ソーシャルセリングのオペレーションフロー・見るべきKPI」
- 「ソーシャルセリングをやらないといけない理由」
- 「SNS発信を外注すべきか」
ついてお話を伺いました。
目次
ソーシャルセリングとは?普通のSNS発信との違い
野口
木村さん、本日はよろしくお願いいたします。
まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
木村
株式会社Special One 取締役COO 木村 雄飛です。
木村 雄飛さんのSNS
まず、私の経歴についてですが、これまで4つのステップがありました。
- 1社目:京セラ株式会社 (新卒時代)1社目は「京セラ株式会社」という電子部品メーカーに新卒で入社しました。その会社を選んだ理由は、創業者の稲盛和夫氏の考え方やビジョンに共感し、そのエッセンスを学びたかったからです。大学時代から起業を決意していたため、経営哲学を学べる環境として選びました。
- 2社目:パーソルキャリアでの経験(新規事業・マーケティング)2年間働いた後、パーソルキャリアに転職しました。そこで新規事業やマーケティングの領域に徐々に関わるようになりました。当時は「HiPro (旧i-common)」という社内ベンチャーに参加し、立ち上げフェーズに携わりました。入社当時はまだ3~4年目の事業で、組織体制が未整備な中で試行錯誤する環境でした。
- 3社目:株式会社TYL webマーケティングの事業を立ち上げました。事業開発なので、営業もやりつつマーケティングもやり、組織開発もおこなうような働き方でした。
- 4社目:株式会社Special Oneその後、前職で同僚だった方とよりマーケティングに特化した活動をするために独立し、ウェルビーイングに関する事業とソーシャルセリングを主軸としたBtoBマーケティング支援を行っています。業務委託含めて30名ほど在籍しています。ビジョンは「幸福標準の再定義」で、いわゆる「幸福経営」だったり、個人が幸福になるみたいなところを大事にしてます。一方で、企業経営で言うと利益体質になってないとそもそも人に投資できないので、両方のバランスをとりながら運営しています。
野口
ありがとうございます。
続いて、ソーシャルセリングについて簡単にご説明いただけますでしょうか?
また、経営者による「普通のSNSの発信」と「ソーシャルセリング」の違いについても教えてください。
木村
「普通のSNSの発信」との違いは、基本的に「戦略の有無」だと考えています。
どういうブランディングを自分がしていくのか?あとはその自分のブランディングが他の競合している人たちと比べて目立つのか?とかいわゆる3Cフレームワークの考え方ですね。
そもそもSNSより手前に自社でどういったマーケティング施策を実行するのかなどの戦略も必要です。
- 一般的なSNS発信: 特に戦略なしに投稿を進めて、フォロワーを増やし、広く情報を届ける。
- ソーシャルセリング: 戦略に基づいて特定のターゲット(見込み客)に対し、情報を発信していくこと
といったイメージです。
SNSアカウントを一貫したブランディングの方向性で価値を最大化すれば、認知度が上がって、特定のカテゴリで想起がとれるようになりますし、DMを送ったときにアポイントが取れます。
逆に考えると、ただ発信してる人たちに、フォロワーがたくさんいたとしても、その人がどういう人でどんな価値があるのかってわかんなければ価値につながらないケースがあります。
戦略があれば、たとえフォロワー 1,000人でもアポが取れると考えています。
POINT:ソーシャルセリングと通常のSNS発信の違いは、戦略の有無!
SNSを使わないと勝てない!マーケティングの本質「認知チャネル」からの逆算
野口
そもそも、新しい会社の事業領域として、ソーシャルセリングの領域に目をつけられたのはどのような理由でしたか?
木村
メインのクライアントとしては中小企業が多いのですが、課題感として「そもそもリード獲得できていなかったり、採用できていない」などの問題が大きかったです。
私自身、マーケティング施策は一通り経験があったのですが、時代の流れ的にSNSのインパクトと需要は非常に高いので、ソーシャルセリングに特化したマーケティング支援サービスに注力しています。
今やSNSで会社の代表個人が発信して、会社の認知度を高めたり、採用するようなケースが増えているので、むしろSNSをやってないと立ち行きが怪しくなる時代が絶対来ると思ってます。というかそうなりつつあります。
AIの発展で、今後施策自体のオリジナリティみたいなのはなくなっていくと思うので、いわゆる会社としての思いとか、代表の人柄とか「ヒト」の部分が重視されるようになります。
SNSだと、やっぱり自分の文字だったり投稿によるコミュニケーションができるので、その領域に注力しています。
野口
なるほど。まさに仰る通りのトレンドは今にはじまったことでもないですが、これからも続く流れかと思います。
以前、とあるマーケティング支援会社の代表の方が、「SNSが強すぎて、ほかの施策の優位性がどんどんなくなってきている」という話をしておりました。
おっしゃっていただいたように、そもそも顧客側の認知チャネルがSNSに比重が置かれるケースも多くなってきています。
そこから逆算すると、SNSに注力するのが最もコストパフォーマンスが高いというのも理解できます。
そのうえで、属人性に回帰してる点はまさに、と感じました。
木村
そうですね。本質的にやっぱりユーザーの選択肢が増えたので、カスタマージャーニーがとても複雑化してるんですよね。
従来のセオリーが通用しなくなってきています。
昔だと、そのいわゆる三角形のマーケティングファネルで語れていたと思うんですよ。
最初テレビCMでガンと当たって、認知が増えて問い合わせが増えるようなシンプルなマーケティングですね。
でも、今はテレビもみて、SNSでバズった投稿も見て、ホームページもみて、類似製品の会社のSNSも見て最終的にもう1回ホームページ行って、8割ぐらい意思決定してから購買に至るみたいな形ですね。
そして、今は本当にもうSNSが認知チャネルとして強すぎるので、、認知の網を張らないともう終わりっていうようなイメージがありますね。
野口
「商談前にもう発注先は決まってる」みたいな話もありますが、いかにその第一想起を取れるかみたいな話から逆算すると、やっぱり日々の認知チャネルの中で1回見たことがあるみたいな状態をいかに作るかみたいなのが大事ですよね。
「なんかわからんけど受注に至る」みたいなのは年々増えてきているはずなので、顧客がいるところに、認知の導線を準備しておかないといけませんね。
木村
そうですね。顧客の属性っていう意味合いの解像度の荒さだともう無理で、本当にペルソナでその人の生活がどのようなイメージで、SNSを使って、とテレビを見ているのかとやっぱ想像してた時にそこに数当たれているかが大事です。
手っ取り早くやれるSNSだとXがおすすめです。toCだとインスタも入ってきます。
POINT:SNSは認知チャネルとしての役割が年々強まっている。AIの発展により、施策自体のオリジナリティは薄れていくため、「ヒト」の要素が今後より重要になる。
ソーシャルセリングの3つの軸:アカウントプランニング・作成代行・エンゲージメント
野口
ソーシャルセリングの具体的なオペレーションを知るために、御社の支援の流れを聞かせてください。また、見るべきKPIも教えてください。
木村
プロジェクト1つあたり4名ほどで支援しているのですが、オペレーションの軸は主に3つあります。
- ① アカウントプランニング
- ② 投稿作成/投稿
- ③ エンゲージメント
です。
- ① アカウントプランニング:発信の目的、社長のブランディングイメージ、投稿の文体やトンマナを決めます。
- ② 投稿作成/投稿代行:アカウントプランとペルソナに沿って投稿を作成し、投稿代行まで実施します。基本的に運用についてはクライアントはゼロ工数です。
- ③ エンゲージメント:自社の目的に合ったアカウントへのいいねやリプライ、フォロー等のインタラクティブな活動です。
そして、見るべきKPIとしては、フォロワー・インプレッション・プロフィールアクセスですかね。ほかにも色々ありますが、メインはこの3つです。
POINT:ソーシャルセリングの3つの軸:①アカウントプランニング ②投稿作成/投稿代行 ③エンゲージメント。見るべきKPI:フォロワー数、インプレッション数、プロフィールアクセス数。
野口
なるほど。以前ある経営者から「Xやりたいけど文字書くのとか苦手なんだよね」みたいな相談をうけたことがありました。
それに対して、基本的にSNS支援会社はコンテンツ制作代行は出来るけど、文面でのポストや発信内容を考えて投稿まで請け負うところは経営者との考え方とズレてトラブルになるリスクまで考えると請け負えないケースがあると思うのですが、そのあたりはどのようにカバーしてますか?
木村
私たちの場合は、アカウントプランニングにかなりの時間と工数をかけています。
経営者の考え方を最初にがっつり聞くようなフェーズを1ヶ月取ります。
それをもとに思いやパッションを抽出するのが1つです。
そこから、その経営者さんが使っている文章体をAIに読み込ませて学習して、データベース化します。文字に起こすところは人がやりますが、考え方・文体などは出来る限りAIを使って緻密に設計しています。
毎回発信内容をそのデータベースに合致しているかをチェックしながら作成するので、経営者との考え方のズレは起きないようにしています。
またスピード感を重視するために、毎回チェックしてもらうみたいな運用ではなく、基本的に信頼してお任せ頂いてます。
野口
めちゃくちゃいいですね。
会社によっては、代表のアカウントを社内のメンバー/インターンが代行するみたいなのってたくさんあると思うのですが、逐一LINEで「この文章で行こうと思います」みたいな運用だとスピード感が落ちるのもそうですし、作成する側も結局レビューしてもらうのを想定しながらライティングすると思うので、コンテンツ力が弱くなっちゃってるなみたいなところは想像できます。
リスクコントロールしながら仕組み化しようっていうのは理解できる一方で、スピード感もコンテンツ力も弱くなると、そもそもの最初の目的の「発信してリードを取る」みたいなところからは外れそうですよね。
だからこそ、「投稿を任せてもらう」って簡単そうに聞こえますが、かなり難しいことだと思うのですが、コツを聞かせて頂けますか?
木村
感情的なところでいうとやはり信頼できる立ち振る舞いをしていくことで任せてもいいと思ってもらえることは重要です。ただ、ここを今詳しく話しても再現性がないので、機能的な側面を中心に話すと、やっぱり戦略から入るっていうのが一番大きいかなと思います。
「何を目指したいのか」っていうところを定義し、どういった発信していくのかを決めることで、投稿内容の構造化を行っていきます。
もちろん細かい言い回しの話もあると思うのですが、基本的にはその投稿内容の構造化さえ戦略をベースにできていれば内容はぶれないので。お任せいただけると思います。
SNSのアルゴリズムを理解しないと伸びない。「SNSはセンス」という誤解
野口
SNS運用をやらない会社(経営者)には、炎上してしまいそうっていうリスクが勝っちゃうという考えもあると思うので、それでもやるって経営者は覚悟があるなと感じます。
それを踏まえて、ソーシャルセリングを始める方はどのような考えから始めるに至ったケースが多いですか?また、なぜそれを外注してお願いするのでしょうか?
木村
ニーズとしては主に2つで、① 新規リードの獲得 (新規受注) ② 採用なのですが、「内製か外注のどちらを選ぶか」でいうと、やはりアルゴリズムの理解が意思決定基準のひとつだと思ってます。
例えば、Xはアルゴリズムの変更が本当に頻繁にあるプラットフォームで、昨日まで何もなかった人がいきなりバンされることが普通に起こります。
専門性がない人が運用すると、伸びないし、最悪バンされてしまいます。
野口
アルゴリズムを具体的に言える範囲で結構なのですが、例として何かありますか?
「アルゴリズムを知っていることによって、どういうオペレーションが変わるのか」という意図の質問になります。
木村
私たちは、常時400以上の情報発信のアカウントっていうのをモニタリングしていて、それらを分析して、何がどのようになったか、仮にバンされたらその原因は何かを特定して、リスクとして洗い出しておきます。
アルゴリズムについて分かりやすい例でいえば、、プラットフォーム側は広告収入でマネタイズをするので、投稿ポストに他のユーザーが滞在してるみたいな時間をすごい高く評価します。「投稿やアカウントになるべく長く滞在してもらうためにはどういう仕掛けが必要なんだっけ?」って発想が必要です。
アルゴリズムも頻繁に変わるため、「そのためにどこに一番リソースをかけられるか」を日々アップデートしながら運用しています。
POINT:プラットフォームのアルゴリズム変更に対応するため、継続的なモニタリングが不可欠。ユーザーの滞在時間を伸ばすための投稿設計が重要。
野口
ありがとうございます。
「SNSはセンス」みたいな印象がある方が多いと思います。つまり、完全属人的なものという考えです。
でもお話を伺っていると、「仕組み化は可能」なものってことですよね。
木村
まさにそうですね。
間違いなくどなたでも最終的にしっかり本質がわかればできることだと思います。
そのうえで、SNSは他の施策と比較して、人に価値がつくので、営業面でも採用面でも優位になるため、コストパフォーマンスは高い施策だと思ってます。また、派生してSEOなどほかの施策にも効いてきます。
SNSをやるべき企業・向いていない企業「全員やるべき!」
野口
SNSが向いている企業・向いていない企業を教えてください。
木村
前提として全員やったほうがいいと思います。
そのうえで、どちらかというと、有形商材よりも無形商材のほうが親和性が高いと思います。無形商材の方が、価値提供の軸をいろんな軸から発信ができるので、やはり発信がしやすいですね。
ただこれは、あくまで比率の話なので最初の話の通り全経営者にとって価値が出せます。
商品内容を紹介するばかりが発信ではないので、ご自身の考え方や想いが今は皆さんに刺さりやすいです。
野口
なるほど。お役立ち情報以外のカテゴリなど発信カテゴリはどういうものがありますか?
木村
3つの投稿のカテゴリーがあります。
- インフォメーション
- オピニオン
- ダイアリー
ですね。
わかりやすくいうと、インフォメーションはお役立ち情報、オピニオンは世の中の課題などに対し、自分の意見を出してる感じです。
ダイアリー系は、よりプライベートに即したような内容です。
インフォメーションはやはりいくらでも探せばいい情報があるので、それだけでは価値は出ないと思ってます。一方で、オピニオン系の投稿とかもやっぱり最初から入れても見てくれる人はいないので、発信のバランスは重要ですね。
POINT:インフォメーション(お役立ち情報)オピニオン(世の中の課題や意見)ダイアリー(個人的な出来事や体験)のバランスが取れた情報発信が重要!
野口
ありがとうございます。
最後に、この記事を見ている会社さんなどにメッセージをお願いします。
木村
SNSは先行者利益があると思っています。
たくさんの経営者の方がXをはじめSNSをやり始めてるんですよね。
ただ、今後より難しくなってきて、本当にみんながみんな伸ばせないみたいな時代とかも来る可能性も全然あると思います。
今だからこのアルゴリズムで攻略してこう伸ばせるっていうようなところを、私たちは実行できますので、ぜひご相談ください。
まとめ 【インタビューを終えて】
今回も学びが多いインタビューでした。
まず、「通常のSNSの発信」「ソーシャルセリング」の違いとして、「戦略の有無」と言い切っていただいたのが、とても良かったです。
だからこそ、戦略をどうするか、という部分に注力してからSNS発信代行をするという自社の支援の強みに説得力がありました。
ベンダー側(支援側)の話を聞くと、やはり事例やナレッジがあるからこそ、本質的な部分を聞けるため単なるうまくいった成功事例にとどまらず普遍性がある内容であるため応用が利くかもという点で非常に勉強になります。
株式会社Special Oneの場合は、「戦略部分のナレッジ化」「アルゴリズムの理解」「ライティング」が大きな強みだと思いましたし、外注で想起されるような単なる作業代行ではない点が外注するか否かを意思決定する上で重要なポイントかと思いました。
また記事内でも議論したように、そもそもSNSが認知チャネルとして無視できない規模であることから、SNS発信は絶対にやるべきというのも非常に納得度が高く、最近では集客だけに関わらず、会社経営のメンバーを引き入れる中でも、SNSでの発信力がある人をメンバーに引き入れるという流れも多くなってきました。(ex: SNSでも度々話題に挙がる中古車販売をメインで扱うバディカさまもSNSでの発信力がある方々を役職者として社内に引き入れるというやり方もSNS時代だからこそやる取り組み、という視点ではなく、もはやそれをするだけで会社の優位性につながるという時代に来ているような気がします。)
やるやらないは各社の商材とのマッチがありますが、「リスクがあるからこそSNSをしない」ではなく、やらないリスクはなんだろう、という振り返りは必要かと思います。
さて今回のポイントを振り返ります。
- ソーシャルセリングと通常のSNS発信の違いは、戦略の有無
- SNSは認知チャネルとしての役割が年々強まっている。AIの発展により、施策自体のオリジナリティは薄れていくため、「ヒト」の要素が今後より重要になる。
- ソーシャルセリングの3つのオペレーション軸:①アカウントプランニング ②投稿作成/投稿 ③エンゲージメント。
- 見るべきKPI:フォロワー数、インプレッション数、プロフィールアクセス数
- プラットフォームのアルゴリズム変更に対応するため、継続的なモニタリングが不可欠。ユーザーの滞在時間を伸ばすための投稿設計が重要。
- インフォメーション(お役立ち情報)オピニオン(世の中の課題や意見)ダイアリー(個人的な出来事や体験)のバランスが取れた情報発信が重要!
ソーシャルセリングに注力して取り組みたい企業は、ぜひ株式会社Special Oneさんにお問い合わせください。
以上。