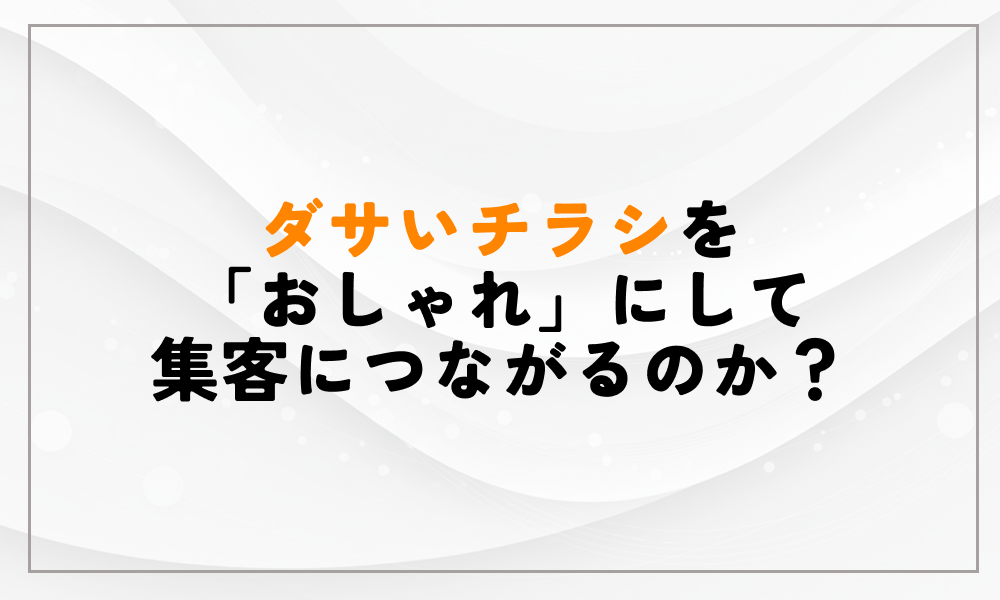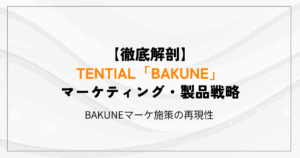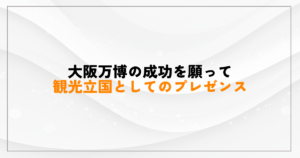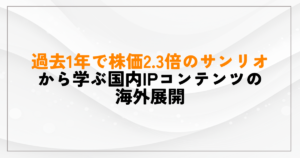これは、チラシに限定した話ではなく、バナー/動画/ホームページなどあらゆるクリエイティブに敷衍できる内容かと思います。
マーケターやデザイナー視点であれば、「こんなダサいクリエイティブで集客つながるんかい!」と直感的に思ってしまうことも多いと思います。
「おしゃれ」とは何か、という定義からはじめてしまうときりがないので、一旦それは考えません。
重要な論点ですが、私がそれを説明しきれるほどの「おしゃれ (デザイン)」に関する知見がありません。
「ダサい」クリエイティブのペルソナは誰か
さて、「ダサい」クリエイティブが及ぼす具体的なデメリットとして、
「ダサいなぁ、なんかうさんくさいなぁ」「ブランディング毀損しないか?」というイメージを持たれてしまう信頼性のリスクがあります。
一方で、それに対して “ダサいクリエイティブのほうがいい” ケースがあるとしたらどのようなものでしょうか。
ここで体験談を共有します。
知人が、スピリチュアル系のサービスに携わっていた時に、クリエイティブを見せてもらいました。
パッと見て、「めちゃくちゃダサい!むしろあやしい!」と感じました。
しかし、お客さんはめちゃ集まっているのです。
クリエイティブをおしゃれにすれば、もっと集まるという見方もたしかに間違いではありません。
ただここで大事なのは何か。
それは、顧客は誰かという話です。
具体的に言えば、当該領域の想定お客さんのインスタの投稿などを見ても、先ほどみたクリエイティブと同じようなデザインだったのです。
「おしゃれかどうか」はバイアスの積み上げで主観的に判断されるものなわけで、想定ペルソナにあったデザインが大切なわけです。
上記で、スピ系のサービスの事例をあげましたが、不動産、リフォーム、金融サービスなどでも同じ事例をたくさんみてきました。
ABテストをした結果の「ダサい」
さて、日本の代表的な事例を挙げれば、Yahooさん や 楽天さんもおしゃれか?と言われれば、どうでしょうか。
デザイン単独で見れば、洗練されているとは言えないと感じる人も多いかと思います。
しかし、日本でもトップクラスに広告費をかけてやっている会社です。
あれだけ広告費をかけている会社で、社内にも国内トップクラスのマーケター/デザイナーがいるはずです。
サイトのリニューアルやABテストをしていないわけありませんから、結果としての「おしゃれでない」ホームページです。
つまり、「お客様にとってベストな状態」ですね。
こういった企業様はデザイン(UI)だけではなくサイトとしての情報設計(UX)を加味した上でデザインを決めているわけなので、一概に同じ抽象度の話ではありません。
ブランディングにおけるデザインの話に派生すると、ブランディングとは洗練された美しいデザインであればあるほど良いわけではありません。
たまに、ホームページをリニューアルしたい企業様に、どういうデザインにしたいですか?ときくと、「NIKE」「Netflix」「Apple」のようなサイトを理想として掲げる企業様もいらっしゃいます。
気持ちはとてもよくわかりますが、結論、難しいです。
※ 単純に 「(下手したら歴史上)世界でも0.1%以内に入るデザイナーチームが完璧に設計したデザイン」を再現する難易度は超高いので技術的にできません。(少なくとも私は今回の人生では出来ないでしょう。)
大切なのは、自社の想定顧客にあったデザイン、情報設計にすることです。
ブランディングデザインに限らず、「ブランディング」というと、たまに「洗練された美しいデザイン」に作り替えて、ブランドイメージを一新して知名度を上げること、という意味合いでお話しされている方もいます。
結果的にそうなるかもしれませんが、それはあくまでも手段です。
そして、手段にこだわってしまうと、一方向的に企業から顧客に「私たちのブランディング」を伝え続ける本末転倒な結果に陥ります。
難しいですね。
「ブランディングが先か」「ペルソナが先か」
(ここまで書いて恐縮ですが、) しかしながら次の観点を忘れてはいけません。
企業のブランディングの醸成が顧客の頭の中にあるブランディングイメージを左右します。
つまり何が言いたいかというと、鶏と卵問題。どちらが先かというのはわからないということです。
わかりやすさのために、先のスピ系のサービスの話をすると、その界隈でこういうデザインが一般的になっているからこそ、それが好きな顧客もそのデザインに依ったトンマナが好きになるわけです。
Apple製品のデザインが好きな人にはミニマリストが多い or なりやすい、みたいなロジックです。
※ これはデータがないので、統計的に有意にそうであるとは限りません。
ブランディングとは、デザインやコーポレートアイデンティティを確立すること (WHAT)に注力されがちですが、それをどのメディアでどのように伝えるかという (WHERE/HOW)がセットであるべきで、その前段階として (WHO)が前提になります。
とてつもない広告費(もしくは知名度)があり、サービスも革新的であれば、堂々と (WHAT)を確立した後に、それをあらゆるメディアで力技で浸透させて世界中にファンを作ることは可能でしょう。
しかし、現実的に多くの企業が従うことが可能な戦略かといわれれば、そうではないでしょう。
市販されているマーケティングの本を読むと、なんか違和感を覚えるのはこのような背景があるからです。
大学のマーケティングの講義やゼミのマーケティング論でも、だいたいこのようなケーススタディをやりがちですが、実用性の観点からは妥当性を疑うばかりか、原理原則の間違った理解が進む弊害があるのではと推測します。
(※ 私は商学部出身で似たような講義を受けますが、一面的な見方だなと感じることは少なくありませんでした。原理原則がそうだからと言われても、実態とそぐわず実用性がなければ、その理論の価値は下がると考えます。)
かつて所属していたクライアント様の業務の一環でマーケターの採用面接をしたときに、マーケティングの未経験の方でしたが「御社に入ったら、マーケティングの戦略は学べるのでしょうか?」という質問がありましたが、おそらくその方がイメージしている戦略はそのような戦略をイメージしているんだろうな、と感じて、不安になったことを思い出します。
以上です。