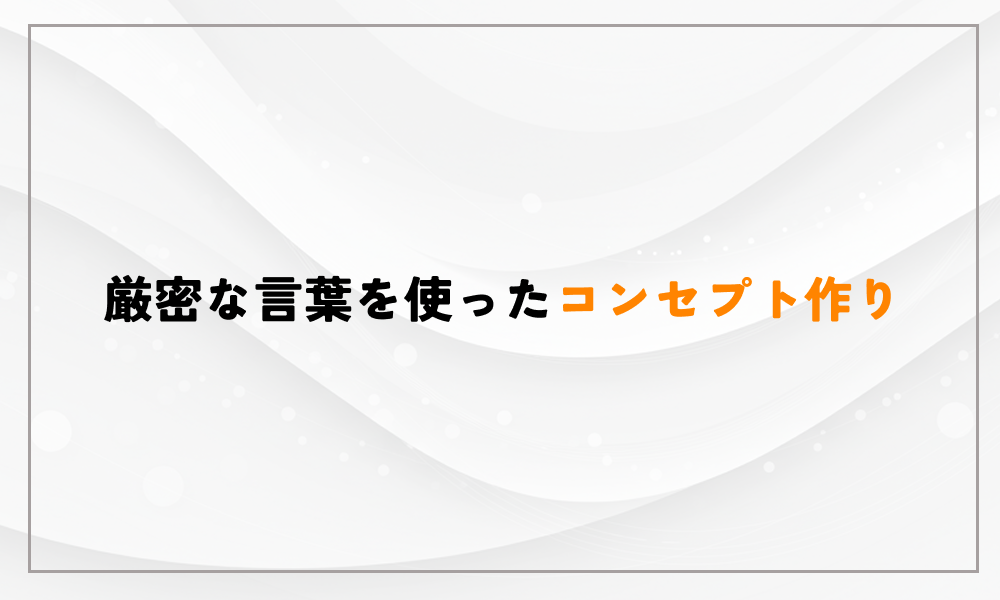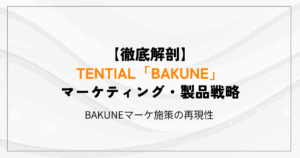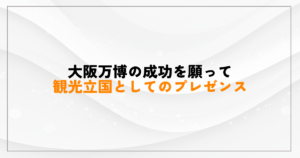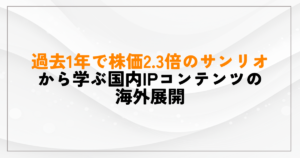最近、とあるIT系のクライアント様とサービスコンセプト作成のための議論を行いました。
代表の方と、ホワイトボードの前に立って、二人であーだこーだと話しました。
営業資料や、ホームページなどで使用される想定で、サービスの価値を端的にイメージ出来る文言を作ることが目的です。
課題は、サービス自体が専門的でわかりづらく、サービスの良さが一言で伝わらないことでした。
(逆に言えば、細かく説明が必要なぐらいに専門的であることが同サービスの強みです。)
しかし、一言でイメージがわかなければ、興味関心すらもってくれません。
営業の現場でもそうですし、資料/HPそれぞれ単独でもそうです。
前のめりな姿勢で、さぁサービスを理解するぞ!と考えながら説明を聞いてくれるお客様は極めて少ないでしょう。
さて、短くサービスのコンセプトをまとめるためには何が必要だろう、という点からクライアント様とお話ししました。
(※ サービスコンセプトの作り方に関して、手順として適切なフレームワークを持ち合わせてはおりません。ある程度この筋から進めるのがいいだろうな、というざっくりステップは思い浮かびましたが、仮にもう一度やれといわれても、まずはそこからクライアント様と一緒に考えるところから始めるだろうと思います。そもそも、フレームワークを書き進めるだけでうまくいかず、結局は参加者の信頼関係が必須です。)
軸として大事なのは、「ユーザーの便益を分かりやすく伝えること」です。
ユーザーは”情報”ではありません。”人”です。
なぜこんな不思議な言い回しをするかというと、結局そのユーザーの便益とは何か、と考えるときに、その人の生活/人生を想像することが必須だからです。
ユーザーを”情報”と捉えると、便益をサービス提供者側の都合で考えてしまいがちです。
そして、便益とは点ではありません。急に特異点があり、変化が起こって、便益が得られるわけではありません。
便益に至るまでの流れが常にあります。そのストーリーを想像します。
「そのユーザーは、今どんな状況にいて、どんな気持ちでそのサービスに触れて、どんな気持ちになって、結局どんな便益を得て、どんな変化があるだろうか。」
これを想像する必要があります。
これを想像するためには、
誰にとって、「どんなイベントが起こって」「どうなるのか」
ということをまず考えて、それを具体的に想像するのが良いでしょう。。
さて、ここまでが長い前置きでした。
ここで、タイトルにある「厳密な言葉を使うコンセプト作り」のが大切だという話をします。
例えば、経理システムがあるとしましょう。
「経理を自動化することで、仕事がもっと楽になる」というコンセプトがあったとします。
(※ ちなみに、バイアスをなくすために、どの経理システムのサービスページも見ていません。ですので、もし似ているコンセプトを謳っているページがあれば申し訳ありません。もし、似たコンセプトでしたら、是非一緒にコンセプトを作り直しませんか。冗談ではありません。もちろん煽っているわけでもありません。純粋に一緒に考えるプロセスを楽しめたらなあと考えています。他意はありません。)
話を戻します。
「経理を自動化することで、仕事がもっと楽になる」
私はこれを仮に見た場合、
① 経理を自動化するってなに?
② 自動化されたら、なんで仕事が楽になるの?
③ 仕事が楽になるってどういう状態?
と思っちゃいます。
わざわざ分けましたが、①②③は同じことを言ってます。
コンセプト関係なく、あるあるだと思うのですが、文と文(単語と単語)のロジックが厳密ではないのです。
「直感的にはイメージ出来るけど、もっと厳密にするべきロジック」
簡単にいえば、言わんとしていることはわかるが、なんか余白があるなぁ、というロジックです。
ここで一旦立ち止まります。
なぜこんなことが起こるのでしょうか?
「経理を自動化することで、仕事がもっと楽になる」
このコピーを思いついた人のワードセンス(文章力)が不足しているのでしょうか?
もしかしたら一理あるかもしれませんが、結局は「ユーザーのことを想像できていないから」に尽きるのだと思います。
ユーザーの”生活”を、”悩み”を、”変化”を想像していないことが原因なのです。
結局、ユーザーにとっての便益のような言い回しに聞こえるのですが、企業側が伝えたい便益に過ぎないのです。
「どんな作業を自動化したいんだっけ?」
「そもそも、なんで経理を自動化する必要があるんだっけ」
「今具体的にどんな作業に悩んでいるんだったっけ」
「その作業しているときのユーザーの気持ちはどんなものだろう」
「そのユーザーはどんな人なんだろう?どんな仕事への向き合い方をしている人なんだろう。」
「そのユーザーは仕事のどこを改善したいと思っているんだろう?それはなんでだろう」
「そのユーザーは、はじめてあなたのツールをみたときにどんな気持ちになるのだろう」
「触ってみて最初になんて言うだろう」
「触ってみて、業務が改善されたときどんな気持ちになるだろう」
「業務にどんな変化が起こって、その人はどう変わるんだろう」
あくまでも一例ですが、小説のようにいろんなことを考えるのが大事です。
おおげさなぐらいその人に思いを馳せる必要があります。
ちなみに、全然関係ないですが、かつて、私はGoogle Suite(現:Google Workspace)をはじめて導入して触った時、Office365 and 社内オンプレサーバーから解放され、快適すぎて人生が救われたという気持ちすらしました。導入を担当してくれた代理店のシステム営業担当者に感激の電話を何度もいれました。
ユーザーの想像し、結局厳密な具体的な言葉を使いながら、ロジックを厳密にし、コンセプトを作り出すことが必要です。
今回のワークでは、正解かはまだわかりませんが、ユーザーの気持ちと便益が想像できるコンセプトが仕上がったと思っています。
長くなりましたが、以上です。