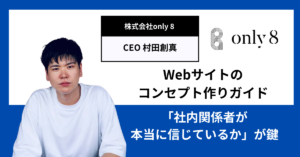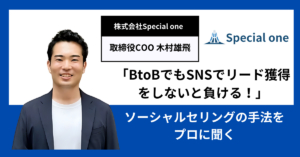今回は、SaaS企業の立ち上げの注意点を解説するインタビューです。
SaaS企業のビジネスモデル・MVPまでのベストプラクティスは、SaaS企業経営者・VCなどが情報発信することが多く、他の業種より情報が多いように思えます。
一方で、実際に立ち上げていく中で具体的な悩み、立ち上げからどのように顧客を獲得したかなどの実体験はまだあまりみかけません。
今回は、「生成AI x SaaS」の文脈でマーケティング領域の工数削減を目指す事業を行っている株式会社Insight scienceの代表・村上和也さんにお話をお伺いしました。
今回は
- 「現在の事業をはじめるまでの事業領域の発見」
- 「ローンチまでのMVPプロセス」
- 「立ち上げ後の苦悩」
- 「競合との差別化」
- 「初期段階の顧客獲得方法」
などについてお話を伺いました。
目次
10年の広告運用業界経験からのプロダクト開発!
野口
村上さん、本日はよろしくお願いいたします。
まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
村上
株式会社Insight scienceの代表の村上です。
「(SEO記事制作、SNS、動画を活用して)集客を、10倍ラクに」するためのAIライティングツール「UniCopi」を提供しています。
キャリアとしては、大学卒業後に独立系SIerに就職し元々エンジニアでした。その後、株式会社アイレップへ転職し、マーケティング領域になり、主に広告運用領域に携わりました。最終的には、アイレップとカナダのacquisio inc.との合弁子会社アクイジオジャパンに転籍して取締役などを経験したのちに、現在の株式会社Insight scienceを立ち上げました。
もともと、起業した当初の思いとしては、頑張る人を助けたいというのが根底にありました。そういった人の中には、自社のプロダクトを作っても売れないからつぶれちゃうという状態になります。本来、クリエイティブテストを突き詰めれば、広告パフォーマンスがよくなって事業がうまくいくというケースもありえたかと思います。
野口
ありがとうございます。
Web広告の代理店の業界でもトップクラスの企業で経験を積まれた後、起業されたんですね。
村上
10年ほどWeb広告の領域に関わってきたのですが、この領域は外から見るのと違って、「かなりアナログな世界」だったんですね。
「このオペレーションのデジタル化は絶対しないといけないな」という思いがありました。
特に、改善が必要だなと思った広告領域は、「クリエイティブ」の部分ですね。
広告運用の現場では、一部の案件を除き「クリエイティブテスト」に時間がかけられていないことが多いんです。
ROIが20~30%改善する余地があるのにもかかわらず、テストされていないというのが常態化しています。
この状況は業界構造に由来します。
というのも、広告代理店はマージンでビジネスをしているため、クリエイティブテストするとテストのための検証工数、提案工数、レポート工数が増えるんですよね。その結果、CPAが下がっても、お客様の満足度は高まりますが、代理店として売上が直接的に増えるわけではないですので、営業会社であればあるほどテストを増やすという力学が働きにくいのだと感じました。
クリエイティブテストをしてもCPAが上がってしまうリスクもあるため、インセンティブがなく取り組めないという構造になります。
私のアイレップ所属時代は、営業数字を一切持たされず、目の前の成果改善に執着させてもらえる環境だったのです。それがとても稀有な状態であったことに、ようやく気づいたのです。
野口
なるほど。
たしかに、広告運用は近年クリエイティブテストすら自動化も進んできていますが、それでもなお広告運用者の手動の運用管理は依然多いですし、仮にテスト結果のCPAが悪いと、それでクライアントからマイナスな印象を持たれてしまったり、最悪契約を切られてしまうリスクを考えると、たしかにインセンティブが働かないかもしれません。
村上
クリエイティブテストよりも、入札調整、つまり予算のアロケーションの調整のほうが工数も低く、確実性も高いため、どちらかというとそちらの調整に注力する運用者が多いように思えます。
野口
たしかにその点はイメージできますね。
「このキャンペーンのパフォーマンスがいいから、このキャンペーンに予算を振ろう」とか「除外キーワードの設定をしよう」とかそのあたりですね。たしかに、短期的にみると、そのあたりの調整によるCPA改善の期待値は高いですし、そこに注力するのは業界構造から考えるとたしかにおっしゃる通りですね。
取り組むプロダクトのスコープの決め方。業界トップクラスの知見をもとにしたプロダクト構想
野口
プロダクトを作るにあたって、具体的にどのような課題に着目しましたか?
村上
当初は、分析面を自動化することに取り組もうと考えておりました。
ただ依然としてそれだけでは改善には向かわないため、PDCAの「C (チェック)」は出来ても、「A (改善)」には向かわないですし、「P(計画)」も立てられないことは課題としてありました。
2016年ごろにはじめたサービスで言うと、具体的にいうと、「実験計画法」というのがありまして、その検証方法をプロダクトに反映したサービスでした。
簡単に言えば広告文を分解して、フレーズ単位で「A/B」に分けて、3か所ぐらいに差し込むと、全部で8通り(2 x 2 x 2)あるわけですよね。それを実験計画法を用いると、多変量解析で分析することで、より少ない4パターンで出来るといった具合です。
「少ない工数で、どの広告文が一番最適か」が分かるサービスです。
野口
当時の反響はいかがでしたか?
村上
結論から言うと、あまりうまくいきませんでした。
おもしろいね、と受け入れられることはありましたが、実際の導入になると「実際の検証パターンをどう考えればいいのかわからない」となりました。例えば、コピーAとコピーBを差し替えたらどうなるか、男性の画像と女性の画像を差し替えたらどうなるかなどクリエイティブの検証パターンを作り出し、テスト計画を考える必要があったのです。
サポートが必須になるため、その検証パターンを考案する業務自体を受託して当社がツールを代行して使う形がほとんどになり、SaaSとして独立して導入してもらうのは難しかったです。
しかし、生成AIが出てきたタイミングで「技術的なシフト」が起こりました。
これまで手作業で行っていた広告の検証パターンのアイデアを考える業務が生成AIによって一気に「自動化」できる可能性が進みまして、まずはそちらの広告文やコピーアイデアを考えるツールを開発し、その後派生してSEO記事の生成に幅を広げました。
野口
生成AIによって、ペルソナも導入メリットに大きな違いはなかったものの、技術シフトにより「オペレーションフローの効率化の余地」が生まれたわけですね。
POINT: 技術シフトによって、従来のオペレーションの一部が変数化する!技術シフトに伴い「変数化される点はどこか」を予測すべし
ちなみに、事前の事業スコープのリサーチなどは行いましたか?
村上
実は、独立してからリサーチをするというステップはなかったです。
私自身もともとアイレップでR&D部門にいて、広告改善ツールを調べて導入するという業務を行っていましたので、世の中にどんなツールがあって、どういう領域をカバーしているのか、というのはリサーチしつくしていたんですよね。
ただその中でも、「クリエイティブテストを支援する」というツールはなかったので、この領域で戦うべきだと考えていました。
ですので、当時そのプロダクト領域で戦うと決めたときに、当時の同僚にヒアリングして、こんなプロダクトがあったらどうですか?とヒアリングしていました。
野口
それは素晴らしいアドバンテージですね。自身が業界トップクラスの現場感をもっていて、その課題感を認識しており、既存で解決するツールがなかったという状態だったわけですね。
POINT: 事業ドメインへの知識が深ければ深いほど、業界の負に気づきやすい!業界ドメイン知識は強固なアドバンテージ!
後悔しているテストマーケティングフェーズ。SEO記事生成機能が市場にマッチ!
村上
テストマーケティングのフェーズは振り返ると、失敗でした。
プロダクトをすぐに作ってしまったんですよね。
Excelベースでもいいから、とりあえず検証するフェーズを挟むべきでした。
その発想に至らず、まずプロダクトを作ってしまいました。
私自身もエンジニアだったので、自身でプロダクトを開発したので、開発コストとしては費用かかってないですが、時間的ロスはありました。
「初期からSaaSという見せ方にこだわってしまった」のは後悔してます。
野口
ちなみに、当時に立ち返ってみて、Excelでやるとしたらどのようにテストマーケティングしますか?
村上
UIを全部Excelにして、受託モデルで我々が手作業で仕上げて納品するだけでも、だいぶ時間のロスはなくなったかと思います。
最低限のニーズはそれで把握できたかと思います。
一方で、これは今でも悩みどころではあるのですが、「Excelベースのプロダクト」と「SaaSベースのプロダクト」のニーズが必ずしも一致するわけではないというのはありますね。
野口
テストマーケティングの重要性は、SaaSだけに限らず、さまざまなプロダクトで重要視されているフェーズですが、たしかに、MVPとプロダクトのニーズの不一致とのバランスも難しいところですね。
POINT: テストマーケティング時のMVPは最小限で検証すべし!
続いて、ある程度ニーズとフィットしたタイミングはどのようなときでしたか?
村上
SEO記事生成のソリューションが売れ始めたタイミングですかね。
ポイントとしては、2つあります。
① ターゲット
② ペインの深さ
の2つです。
ある時、お客さんから「SEO記事の制作にめちゃくちゃコストと時間かかってて、生成AIでどうにかできないですかね?」と相談いただきました。
これまでは広告クリエイティブの検証は、ニーズが顕在化していないことが多かったんですよね。
営業でも、「クリエイティブテストをすると、こんなに良いことがあるんですよ」というニーズの喚起が必要でした。
しかしながら、生成AIの記事制作では、顕在化していて、すでに困っている状態でした。
野口
めちゃくちゃ面白いですね。
「導入効果」よりも「イマのニーズの深さ」が重要だった、というお話ですね。
POINT: 「導入効果」よりも「イマのニーズの深さ」!導入効果を訴えても、顧客には刺さらない!
「プロダクト力」だけではないPMFの要因
野口
現段階では、PMFをしたと感じますか?
村上
今はしていないと思います。
正確に言えば、PMFの検証を進めていない状態です。
同様にSEOのAIツールを提供する競合の企業さまにあったときも、「最近やっとPMFしたと感じました」とおっしゃられていて、「業界的にPMFしている企業がある」ことは認識していますが、後発で戦っている弊社に置き換えたときには、まだ差別化要因が足りないと感じています。
PMFには、プロダクト力だけではなく、マーケティング力も関わってきます。
ですので、単純に「SEOの生成AIツール」という観点でいえば、認知を取ったもの勝ちという側面があります。
それを踏まえると、たとえば資金力で勝ちに行くなどの力技が必要となるケースもあります。現状はそういった競争をするフェーズではないと考えています。
加えて、現状まだニーズにあわせた機能開発の余地も大きいと感じていますので、使ってもらってメリットを感じてもらうという活動を続ける方針です。
野口
面白いお話ですね。
PMFについて、ちょうど最近考えてたのですが、個人的にさまざまな会社のPMFを調べている中で、「コンセプトを変えてうまくいった」みたいな事例を見かけます。
個人的に、「コンセプトを変えてうまくいく」はやや懐疑的ではあって、そういった企業でもなかには、コロナなどの「外的要因の変化」があって、「消費者心理が変わった結果そこにうまくあてはまった」みたいなケースもあります。このケースで言うと、変数としてはコンセプトを変えるよりも、「外的要因の変化」の変数が大きいです。
それよりも、村上さんがおっしゃったように、「認知チャネル(集客チャネル)と合致した」みたいなケースが多いように思えています。もちろん、単一チャネルでうまくいくみたいなケースばかりではないですが、たとえば記事広告など競合などはあまり手を付けていなかったが、そのメディアを見ていた人たちに「潜在顧客」がおり、うまくいったみたいな事例ですね。
とはいえ、その顧客がみたときにわかりやすいコンセプトであるというのは重要ですよね。
村上
そうですね。
「買う理由付け」という意味では、わかりやすいコンセプトがあるとやはり営業で入り込みやすいですね。
野口
ちなみに、コンセプト以外の話で、オペレーションであったり、ビジネスモデルで「ツールを使いつつ、裏側でプロフェッショナルがサポートする受託モデル」などは検討されたことありますか?ビジネスモデルを転換するとまではいかなくとも、サービスを拡充するためのアイデアとかあればお伺いしたいです。
村上
もともと、SaaSモデルとしての拡大にこだわっていたのもあって、受託モデルは出来る限りやらないようにしていました。
でも、たしかに日本では、SaaSモデル単体では難しいケースが多く、そこにこだわらず、ニーズに沿うのであれば、サービスの拡充は考えていますね。
初期マーケティング施策は「交流会」で獲得
野口
初期のマーケティング施策として、パフォーマンスがよかったのは何だったかお聞かせください。
村上
「交流会」ですね。
ツール自体も比較的安価に導入できますし、実際に会ってお話しすると課題などもヒアリングできますし、その場でニーズにあった提案もできますので、交流会との親和性は高いかと思います。
「交流会」でのつながりをきっかけに、SNSでのつながりも増えるため、発信力も高まります。ありがたいことに、そういったつながりからのリファラルもあります。
野口
たしかに交流会に参加している人は集客にお困りの方が多いと思うので、親和性の高いツールですよね。
POINT: 担当者決裁レベルの価格帯であれば、交流会は有効!交流会でのつながりはSNSでの発信先として貴重な資産になるため、積極的にSNSを交換すべし!
最後に、これからSaaSプロダクトの立ち上げを検討している方へのメッセージがありましたら、お聞かせください。
村上
さきほどの後悔のところでも言いましたが、「経験者の話を聞く」というのは大事だと思います。
技術力があるから、営業力があるからと、いきなりやろうとしても、どんな経験が生きるかもわからないです。
事前に経験者に聞いた話で知っているか知らないかだけで回避できるリスクはたくさんありますので、ぜひ経験者の話を聞くのがおすすめです。
まとめ 【インタビューを終えて】
今回も学びの多いインタビューでした。
かなり言いづらい情報も積極的に開示してくれる村上さんには非常にありがたいと感じます。
今回のメインテーマであるしくじりのポイントは、テストマーケティングフェーズでした。テストマーケティングフェーズで出来る限り「売れるかどうか(需要があるかどうか)」を確認するというのは鉄則ですが、頭でわかっていてもそれを実行できるかどうかは別ですし、インタビューでも出たように「ExcelのUI」と「SaaSのUI」で需要が変わる点も見過ごされがちです。「MVPの最低限」をどこまでやるのか、が論点としては存在するかと思いますが、最低限の機能開発は最小限にとどめるべきで、今やNoCodeで開発できるため、SaaSライクなUIで試したい場合はそれらを活用してもいいかもしれません。
そして、今回のおもしろいなと思った点として、事業立ち上げ時のリサーチで村上さん自身が前職で研究していた分野であり、「ドメイン知識」は深かったという点ですね。
自分が詳しくなくてもニーズに合わせて、サービスを作るというのも一手ですが、やはりドメイン知識が深ければ深いほど、サービスの差別化になりやすいですし、サービスへの思いも乗りやすいので、事業を継続するための熱量も保てます。
以前、【マーケ事例】「交流会イベントを主催して、売上につながるの?」人気イベント主催者が語る裏側と戦略で、交流会を主催する側は売上につながるのか、というインタビューを実施しましたが、今回は交流会参加者側も売り上げにつながっている、ことが分かりました。特に、担当者決裁レベルでも導入しやすい価格帯で、かつ代表の村上さん自身がサービスの説明をしている、という点も、先ほどの「ドメイン知識の深さ」と相性が良いように思われます。
本インタビューをまとめます。
- テストマーケティングはコストを最小限するために、最低限のUIでヒアリングをすべし。
- 「導入効果」よりも「イマのニーズの深さ」に着目すべし。「やってみて効果が分かる」は説明しづらく、導入の意思決定要因としては弱い。
- 担当者決裁の価格帯は、交流会でも成約を生む。交流会で知り合った人とSNSでつながりを増やし、レバレッジを効かせることも有効。
- 「技術シフト」によって、これまで固定化されたオペレーションが変数になる。従来のオペレーションのどこが変数化しそうか予測すべし。
- 新規事業を始める際は、似た事業を行ったことのある経験者にヒアリングし、できる限り不安要素を特定すべし。
以上。