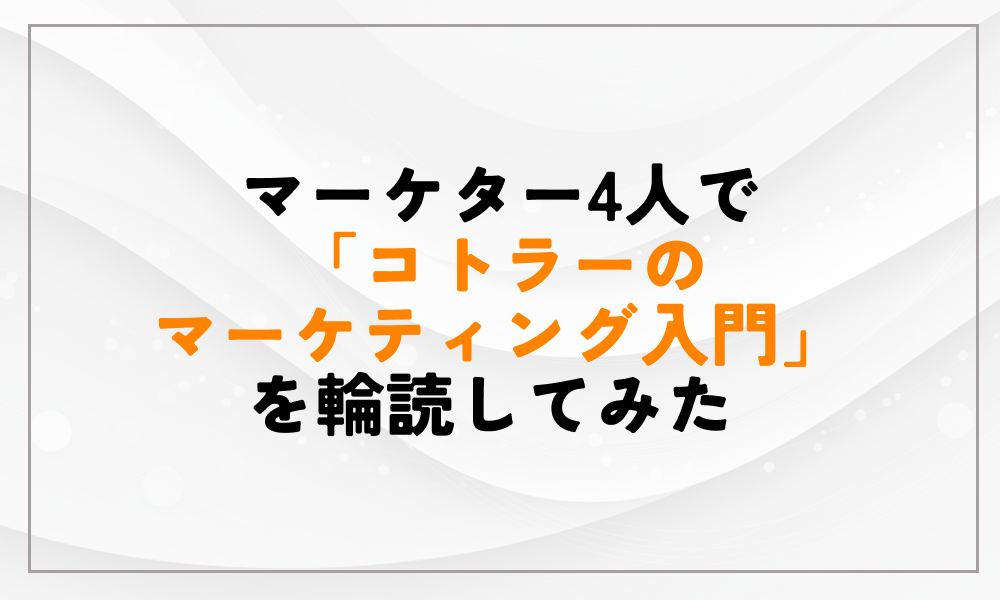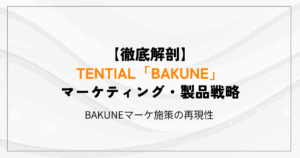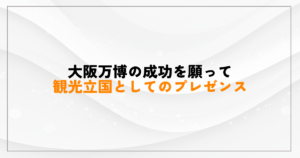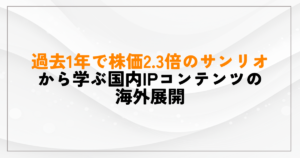目次
1. 「コトラーのマーケティング入門」の輪読会のきっかけ
マーケティングのプロを名乗っているからには、マーケティングの学術書よんで、本質的な部分の理解を深めないとなと感じたからでした。
さっそく、前職の同僚3人に声をかけ、即時承諾してもらえました。
私を含め4名で開催。
私以外は、LINEマーケティングのプロフェッショナル、SNSマーケのプロフェッショナル、デザインのプロフェッショナルとそれぞれバックグラウンドも違うため、多種多様な視点から意見を出しあうポジティブな発散効果が見込まれました。
冷静に考えて、こんなに分厚い「コトラーのマーケティング入門」をみんなで輪読会しよう!っていってプライベートな時間を削ってまでも集まる仲間を持っているだけで本当にありがたいなぁと思いました。
それだけで輪読会実施の元がとれていると本気で感じます。
2. 輪読会の実施方法
参加者は4人で、全16章を2章ずつローテーションし実施したので、4人 x 2名 x 2週だったのでちょうどいい人数規模。
(※ やってみて分かったのですが、インタラクティブな交流が求められる輪読会では最大でも4人が上限かなという気はしてます。)
輪読会はどのように実施したのか具体的なフローは下記のとおりです。
頻度:
隔週実施
範囲:
全16章を
毎回 2章ずつ (約100ページ)で全8回実施
事前準備:
各参加者は、事前に指定された範囲を読み、主要なポイントや疑問点をメモしておく。
■ 毎回ファシリテーターをローテーションする
■ ファシリテーターに選ばれたものは、簡単にスライドに内容と要点をまとめてくる。
アジェンダ:
■ ① プレゼン:担当ファシリテーターから内容の振り返りと解説
■ ② ディスカッション:内容の不明点や、実務における事例を踏まえてフリーディスカッション
■ ③ ケーススタディ:章末に挙げられている事例を自分だったらどうするかなどを議論する
■ ④ まとめ:ファシリテーターがディスカッションの要点や新しく学んだ視点をシェア。議事メモを終了後全員に送付。
3. マーケティングを学ぶ上で、「コトラーのマーケティング入門」は実用的か?
「コトラーのマーケティング入門」をマーケティングの理解を深めるために読むべきかという問いがあれば、結論をいえば、たしかに理解は深まりますが、あまりおすすめはしません。
マーケティング学ぶなら、読むべき!と強く推奨するほどではないかなと感じます。
少なくとも、書店でよくみられるキャッチコピーである「すべてのビジネスマンにおすすめ!」みたいな本ではありません。
当然、勉強のための勉強として本を読んでみたい、という興味関心は全く否定しませんが、もし、マーケティングを学びたいという方がいたら、お勧めする本ではありません。
実際、そういう相談を受けることがありますがその時は、いくつかより実践向きな本を紹介します。
(※ やや話はそれますが、勉強のための勉強は否定されがちですが、私は全く悪いと思いません。しかし、マーケティングを学ぶ上で、という前提を加味すると、実用できるか?という問いはセットであるべきだと思いますし、このブログを読む人のためにもあえてそこはポジションをとってお伝えできればと思います。)
ここで誤解していただきたくないのは、「コトラーのマーケティング入門」を読むのが実用的か、という論点であり、ほかの学術書ならまた変わるかもしれません。
くわえて、そのあとコトラーは、多数の著書を出していて、それはまだ読んでいない段階ですので、それらを加味するとまた変わるかもしれません。
また、「コトラーのマーケティング入門」の扱っているケースや前提情報が古く、事例の粒度もかなり荒いため、見方をかえれば、結論ありきの主張になっていることもあるからです。
扱われている「素晴らしい企業の事例」が最新情報ではシェアを大きく奪われていたり、当該業界でのプレゼンスがかなり低かったりします。
(競争優位性は常に変わりうるため、もちろん当時にそれを予測できるわけないですから野暮な指摘でもあります。)
4.「 コトラーのマーケティング入門」を学んで良かった点、輪読会の良い点
「 コトラーのマーケティング入門」は大企業の過去の事例などを取り扱いながら、各種フレームワークなどが展開されます。
それらは、特にマクロ環境やマクロな問題を分析する上で、情報を切り分けて理解するという点で有効であり、新しい視点が得られます。
一方で、特に後半において、サプライチェーンや、オペレーション部分で、デジタルマーケティングについて展開されることは多いですが、それらは理解したとしても実用の観点からはどうかといえば懐疑的です。
大企業が対象として扱われていることが多いというのもありますが、大企業のマスマーケティングや、サプライチェーンにしても実態はかなり複雑な構造となるため、それらに対する私自身の理解が深くないというのを差し引いても(むしろ深くないからこそ読むわけですが)、書籍で解説されるような部分は抽象的であることが多く、「まぁそうだよね」というレベルで何か新しいインサイトに結びつく情報は多くはありません。
デジタルマーケティングの施策レベルで考えても、Facebookでのページの人気やそれによるブランディングなどの話もありますが、2024年においてFacebookのページやそれによるコミュニケーションブランディングは昔と比べて効果は限定的でそこに割くマーケティングリソースは他の施策と比べたときに劣後してしまいます。
もちろん、その施策が大事という話をしているわけではなく、コミュニティを作る、ファンを作るみたいな主旨のことを伝えたいことではあると思いますが、それはある種自明なものであり、わざわざこの本で学ばなくてもいいかなとは思います。
批判的な書き方が続きましたが、とはいえ、コトラーの主張の根幹として「顧客の価値を想像することが大切である」というベースの思想があり、それも自明なことではあるものの、すべてにつながる大切な考え方であり、それは各章の主張において、繰り返し示唆されているからこそ、たとえば輪読会でも「顧客価値をどう作るかという視点から議論しよう」という共通認識になるため、それは非常にためになります。
輪読会では、今回はマーケティングが専門のメンバーだったので、それぞれの案件の経験を踏まえて話すことが多かったです。
本書に沿った事例共有の場として、議論するのは有益です。
本書のテーマにおいて、もし支援側としてバリューを出すならばという問いを一緒に考えることもありました。
(マーケティングチャネルという視点で、バリューを出すならば、特定地域に詳しい、専門性の高い業者を紹介できる、販促パンフレットのデザインに詳しいなど)
輪読会として、テーマの本を読むと、今この企業どうなんだろう、この情報をうまく整理できるようなフレームワークってないかな?とか調べることが多くなるので、そういった周辺情報も増えます。
たとえば、サプライチェーンに関する販路の話が出てきたときに、「BASE FOOD」のコンビニへの卸しの戦略や、BASE BREADは実は味によって工場を変えているなどが分かります。
基本的に、本書で扱われる事例よりも、調べて得た事例のほうが当たり前ですが、解像度も高く、インサイトも深くなります。
5. まとめ
輪読会の体験は非常にいいものでした。
業務時間とは関係なく、友人たちと抽象的なことも、具体的なことも考えながら思考を発散する体験は非常に面白く、継続的に別のテーマでもやる予定です。
こうしてブログを書いているときにも頭がかなり整理されて、良いアウトプットになります。
やはり学習は人生を豊かにしてくれるなと感じます。
ぜひみなさんも輪読会をやってみてください。
以上